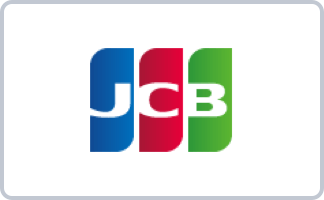家族がみんな隠しごとをしている
¥550 税込
SOLD OUT
送料が別途¥350かかります。
サークル:文章・創作のサークル
ライトノベル短編集
森野ひよこ
家族がみんな隠しごとをしている
マノ・イチカ
はじまりの村の防具屋さん
野原
謎なんぞ、なぞ
ゆにお
野良猫男子。
望月深景
ノスタルジックに恋をして
小鳥鳥子
甘々なアイスコーヒーが良いに決まっている
*
「家族がみんな隠しごとをしている」
もう夕方だっていうのに、ギラギラと熱い日差しが全身に突き刺さるのがわかる。フルートの黒いケースは思いっきり熱を吸収している。大きく息を吐いて気合を入れると、沈みゆく太陽に向かって、毅然として歩を進めた。 やがて家が見えると、越えそうになる我慢の限界を必死で抑えて、玄関へ駆け込む。
「あー、暑い!」
ひんやりとした空気が室内から流れてきて、私は思わず靴も脱がずに廊下に倒れこんだ。 冷たい床の感触が気持ちいい。外の炎天下から一転、至福のひとときだ。起き上がって部屋で着替えるなんてもってのほか。いっそこのまま床になりたい。
「もー、なぎさ! 帰ってきたのに顔出さないと思ったら。何してるのよ、そんなとこで。みっともないわねぇ、誰か来たらどうすんのよ」
見なくてもわかる。母さんが廊下で仁王立ちしている。しかも、年甲斐もなくピンクのうさぎのエプロンをしていると思う。おそらく。でもそんなことを確かめるために顔を上げる労力が惜しい。
「お願い、もうちょっとだけ。今、私、誰よりもこの床を愛してる」 「はいはい。冷たいカルピスあるから、はやくその沸騰した脳みそ冷やしなさい」
呆れた声で言い捨てると、母さんがキッチンに戻っていく。 床が私の熱を吸い取って、ぬるくなってきた。私は大の字に突っ伏したまま、体ひとつ分右にずれる。ひんやりと冷たい感覚が戻ってきて、心地よさに吐息が漏れる。 突然、インターホンが鳴った。 私は飛び起きると、何事もなかったかのように制服を整えてローファーを脱ぐ。
「こんちはー。宅急便ですー」
玄関の扉越しに、威勢のいい声が聞こえる。やはりうさぎのエプロンをしていた母さんは、印鑑を片手にキッチンから小走りで出てきた。私を一瞥すると、しっしっと追いやるそぶりをする。サンダルをひっかけ玄関を開ける母さんと入れ違うように、私はキッチンへ入った。 ダイニングのテーブルには、ペットボトル顔負けの容量のグラスに氷入りのカルピスが入っていた。 さすがわれらが母親。グチグチいいながらも、暑い中部活から帰ってきた愛娘のために、冷たいカルピスを作ってくれている。 私はその母の愛情で、沸騰した脳みそを冷やすべく、のどを鳴らして一気飲みする。冷たいカルピスが、のどから胃へと伝っていくのがわかった。
「んー、最っ高!」
風呂上りにいそいそと缶ビールを開ける父さんの気持ちがわかる。あれは、炎天下のあとの床であり、部活帰りのカルピスなのだ。
「あー、ちょっと、なぎさ! 何で私のカルピス勝手に飲んでるのよ」
発泡スチロールの箱をダイニングテーブルに置きながら、母さんが文句を言う。
「え、これ私に入れてくれたんじゃないの?」 「当たり前じゃない。カルピスぐらい自分で入れなさいよ」
私は口を尖らせながら、クールダウンした脳みそを用いて自己弁護を開始する。
「だって、さっきカルピスあるって言ったじゃん」 「あるわよ。冷蔵庫に。だから勝手に出して作って飲んでよ」 「この真夏日に部活でへとへとになって帰ってきたかわいい愛娘に、カルピスくらい作ってくれてもいいじゃない」 「へとへとでもコップにカルピスと水入れて混ぜるくらいできるでしょ」 「言っとくけど、うちの部はけっこうハードなんだからね。狭い音楽室にぎゅうぎゅうに詰め込まれてみっちり合奏2時間コース。一度代わってみてよ」 「嫌よ。だいたいもう引退なのに、なぎさが勝手に行ってるだけじゃない。あんな壷から蛇が出てきそうな笛の音じゃ、かえって迷惑なんじゃない?」 「失礼! ワタクシ、こうみえてもソロパートありますし!」 「あーもう、はいはい。わかったから着替えておいでよ。じゃないとあんただけヌキにするよ」
突然毒気を抜かれて、私は大きく目を瞬いた。 母さんはさっき届いた発泡スチロールのふたをふさいでいるセロテープをぺりぺりと剥がしている。
「何何? 何が届いたの?」
ふたが開くのも待ちきれず、私は身を乗り出して母さんに問う。
「ふっふっふ。翠さんがお中元にってお肉を送ってくれたのよ。それっ!」
母さんが勢いよくふたを開けると、中から保冷剤に埋もれた鮮やかな霜降りのロース肉が見えた。
「おおー」
思わず二人の声がハモる。 分厚くスライスされた五枚のお肉が、ひとつのトレイに入ってパックされている。それをダイニングテーブルの真ん中に飾り、おおーとか、わあーとか言いながら、しばし二人で愛でた。 ありがとう翠おばさん。大好き。
「付け合せはニンジンでいいかな。あ、ブロッコリーがあった」 「着替えてくるわ」
さっそく冷蔵庫を開けながら悩みだす母さんの背中に声をかけ、私は足取り軽く階段を駆け上がった。急いで楽な服装に着替えて降りてくると、母さんは鼻歌まじりに野菜を下ゆでしていた。
「あ、ねえ、なぎさ。確か冷凍室にラードあったよね」 「ラジャ!」
私は冷蔵庫に駆け寄り、勢いよく扉を開く。すると、扉のポケットに入れていた保冷剤がガラガラと落ちてくる。 うちの冷蔵庫は古くて、冷凍室が一番上の扉で、しかも開けた瞬間ゴーゴー言い出す。必死で冷やしている音を聞いていると、なんだかはやく閉めないと悪い気がする。それでつい目をつぶってしまっているけれど、さすがに今日という今日は我慢できない。 私は保冷剤がクリンヒットした足の甲の痛みにじっと耐えながら、心の中で固く決意する。
「いっつも思うんだけどさ、うち冷凍室詰めすぎだよ。絶対要らないものあるって。少なくともこんなに保冷剤は要らない」
私はそう吐き捨てながら、ポケットに入っている保冷剤を片っ端から取り出して、カップボードに並べる。
「えー、使うことあるじゃん。大きいのと小さいの何個かずつ残しといてよ」 「はいはーい。後で戻しておきます」
不満タラタラな母さんの抗議を、やる気のない声で流す。 アイスクリーム、鮭の切り身、開きアジの干物、豚ばら肉、鶏肉あたりは許す。
「このコップ冷やしてるの誰?」 「あー、父さんでしょ。風呂上りのビール用」 「缶から直接飲んでるじゃん」 「忘れてるんじゃない?」 「はい、ダメー」
私は語尾を下げながら、グラスを流し台へ下ろす。
「次、この化粧水」
サラダ用のキャベツを千切りしていた手を止めて、母さんが訝しげに目を細めて私の持っている瓶を見つめる。
「みかのでしょ、多分」 「う。じゃあ入れときます」
姉さんのものを勝手にいじったら、後が怖い。裏表のないさばさばした人で、脅し文句までが有言実行の徹底ぶりだ。 あったところに向きも元通りに置いておくと、さらに奥へ進むことにする。と思ったら行き止まりだ。巨大な霜の塊がある。
「母さん、この霜なんとかならないの?」 「それねぇ。一度冷蔵庫のスイッチを切ればいいんだけど、こう暑い日が続いてるとやる気になんないよね」
たしかにこの暑い時期に冷蔵庫のスイッチを切ったらいろんなものが傷みそうだ。でもこいつが冷凍室の三分の一くらいを占めている。 私は果物ナイフを取り出して、力任せに掘る。しかし手が届きにくい上に硬すぎで全然削れている気配がない。椅子を冷蔵庫の前まで持ってくると、椅子に登って、冷凍室に頭を突っ込むようにして霜と対峙する。 ふと霜の下のほうに黒っぽいものを見つけた。回りの霜を削って取り出してみると、それは鍵だった。バイクとか車とか家とか、それくらいのサイズ。
「ねぇ、母さん。冷凍室に鍵が入ってるんだけど」 「なっ、はやく返しなさい!」
すぐ私の足元まで駆け寄って、顔面蒼白の母さんは私に手のひらを向けた。私は焦っているような母さんの顔をまじまじと見つめ、鍵を渡した。母さんは半ば奪うようにして鍵を握り締めたが、あれ? とつぶやき手の中の鍵を見つめている──。
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
¥550 税込
SOLD OUT