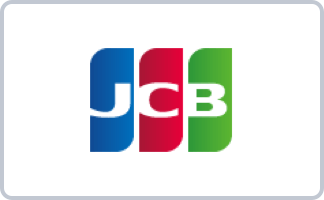ヒキトリノキュウ
¥550 税込
SOLD OUT
送料が別途¥350かかります。
作品
ヒキトリノキュウ
他面綺譚
*
「ヒキトリノキュウ」 著者:黛 沙夜子
都内某所、とあるカフェにて。
隣席の女子大生風の会話。
便宜上、A子B子の二人とする。
「そういえば、来月引っ越しするから荷物の整理してたんだけどさ」
「うん」
「そしたら変なものが出てきたんだよね」
「どういうこと」
A子はテーブルに置いたスマホを手に取った。
「これ」
「えーなにこれ」
彼女たちの席まで少し距離があるため、画面の中は鮮明には見えないが、何か黒っぽいものが写っているようだ。
「これどれくらいの大きさなの」
「これくらい」
A子は両手の指を合わせて○を作った。
「ふつうにボールじゃないの」
「写真じゃわかりづらいけど、切れ目みたいなのがたくさんあるんだよね。それに中に何か入ってるみたいな音がする」
「じゃあケース」
「なのかなあ。全然見覚えないんだけど」
「えーなんか気味悪いね」
数日後、同所。
「例のやつ、持ってきたよ」
「見せて見せて」
A子は、学生がよく持っているような大きな手提げ鞄から、球体を取り出した。遠目には切れ目が入っているようには見えない。B子は、漆塗りのような黒い艶のある球体を持ち上げてじろじろ眺めている。
「これってもしかしてさあ……」
B子は、直径十センチほどの球をA子に返しながら言った。
「おばあちゃんが言ってたやつかも」
「え、なに」
「カイメイさま」
「かいめい…?どんな字?」
「さあ、昔聞いたことあるけど忘れちゃった。なんか」
呪いがどうとかって言ってた気がするけど。
そう言いながら、B子はにやりと笑った。
「えーやめてよー気持ち悪い。私恨まれるようなことなんてしてないよ」
「そう?A子の元彼の○○くんさ……」
彼女たちはそれから球体のことなど忘れたように、恋愛話に花を咲かせていた。私は、手元の本に視線を落としながらも、頭は活字を追うことなく五年前の出来事を思い出していた。
●
「ねえ、これってケンイチの?」
彼女の部屋のソファに寝転がってインテリア雑誌をぺらぺら捲っていると、後ろから声をかけられた。振り返ると、ユキの手に見たことのない黒い玉が握られている。
「さあ。ガチャガチャの景品でも入ってたんじゃないの。捨てれば」
「でもさあ、これ中から変な音がするんだよね」
はい、と玉を渡される。私は起き上がって雑誌を閉じた。
手に持ったときにまず、思ったより軽いなと感じた。それから無機質な見た目のわりに暖かかった。いや、暖かさというよりぬるさ、温泉のあつ湯からぬる湯に移ったときのあのなんともいえない「冷たい」と「暖かい」の絶妙に入り交じったような感覚だ。
「どこにあったの」
洗面台の下だよ。彼女はそう言って玉を奪い取ると、私の右耳に当てた。
「ね」
「ね、といわれても……なんにも聞こえないよ」
「嘘でしょ?」
今度は自分の耳元へ持っていく。
「……やっぱり聞こえるじゃん……音って言うか、間延びした声……そう、お経みたいな」
ユキはそう言った途端、さっと顔を青くして玉を落とした。玉は絨毯の上に音もなく着地した。跳ねることも転がることもせず、衝撃をすっと吸収するように「着地した」のだ。私は本能的に覚えた違和感を押さえ込むように言った。
「なんだよそれ、気持ち悪いな。疲れてるんじゃないの」
翌日、気味が悪いから預かって欲しいと頼まれ、私は奇妙な黒い玉を自宅へ持ち帰った。
その夜、何かの走り回るような音で目が覚めた。それは明らかに人間サイズのものではなく、小動物らしい微かな足音だった。時折ハアハアという荒い息づかいが聞こえる。ホラー映画好きの私は、こんなときには知らないふりを決め込んでじっとしているのが一番だという、確信に近い直感を抱いていた。万が一起きて調べになど行こうものなら、もっと恐ろしい目に遭うに決まっている。仮に私が映画の主人公なら、鑑賞している人間にとっては画にならずつまらないかもしれないが、現実世界では、地味でも構わないから安全を優先すべきだ。私は固く目を瞑り、童話に出てくる愉快な小人を無理矢理に想像しながら、再び眠りに落ちた。
翌朝、スマートフォンの鳴る音で目が覚めた。アラームかと思い止めようとしたら、ユキからの着信だった。
「どういうこと!」
「昨日持って行ってっていったじゃない!」
寝ぼけながら昨夜の出来事をうっすら思い出し「ああ、あのあと帰ったんだな」などとぼんやり思ったが、怒られるので口にしなかった。
「ひょっとして黒い玉のことかな」
「そうだよ!どういうつもり」
「ああ、ごめん、鞄に入れたつもりだったんだけど、忘れてしまったのかも。ところでさ、前から言おうと思ってたんだけど、そろそろ一緒に住まない?」
えっ。
決まりが悪くなると話を全然別な方向へ向けるのは、私が日頃からよく使う手法だ。大抵は「誤魔化さないでよ!」と余計に怒られる結末を迎えるのだが、今回ばかりはうまくいったようだ。彼女の怒りは、一瞬にして鎮まっていた。ユキとの同棲を考えていなかったわけではないが、正直に言うと、具体的に計画していたわけでもない。ただなんとなく、まだ早いかな、などと思っていた。しかし、帰省本能の強い玉のせいで、これから毎朝彼女の怒りに満ちた声で起こされるなんてたまったものではない。
電話を切ると早速、家移りの準備を始めた。とはいえ男の一人暮らしなど、たいした荷物もない。持っている全ての衣類と、愛用の洗面具の数々を詰め込んでみたが、それでも旅行鞄一つで十分足りてしまった。迷ったが、荷物は会社に持っていくことにした。位置関係の都合上、一旦家に帰ると遠回りになってしまうのだ。
「旅行でも行くんですか」
エレベーターで一緒になった後輩に声をかけられる。まさか、同棲を始めるんだよなどとは言えないので、適当に頷いておいた。その日はなんとなくそわそわして、仕事に集中できずにいた。これから始まる彼女との生活に期待しているせいかと考えてみたが、実際は謎の玉のことが頭から離れなかった。少なくとも自分で思っていたよりは、好奇心が旺盛な人間なのかもしれない。時計と睨み合いながら長い一日を過ごし、珍しく定時ぴったりに会社を出て、その足でユキの部屋に転がり込んだ。私の顔を見ると、彼女は黙ってローテーブルの上に置かれた玉を指差した。
「ああ、ごめん。処分した方がいいかな」
ユキは怖い顔をして頷いた。とりあえず彼女の目に触れなければ問題なさそうなので、捨てるふりをして部屋の隅に隠しておくことにした。
しばらくは何事もなく日々が過ぎ去った。ところが、気付かぬ内にユキの身体に異変が起き初めていたのだ。まず、それまでオールAで切り抜けていた会社の健診に引っかかった。そればかりか、どうせ大事には至らないだろうと高を括って受けた精密検査で医者に余命を宣告されてしまったらしい。ショックを受けた彼女は「きっとあの不吉な玉のせいよ!」と、泣きわめきながら訴えた。表向きは捨てたことになっているので、今も自分の近くに玉が存在していることは知らないはずなのに、女の勘というものはいつも鋭い。彼女の一大事であるこの頃、私はといえば、妙に落ち着き払っていた。何故かはわからないが、ユキが死ぬことなんて絶対にないだろうと、確信めいた予感を持っていたのだ。ひょっとしたら、残酷すぎる未来を受け容れたくなかっただけなのかもしれない。このまま黙って年月が過ぎ去るのを見送るわけにはいかないと思ってはいたが、医学知識を全く持ち合わせていない私に病気を治すことは不可能だ。結局自分にできるのは、あの疑わしい黒い玉に対して調べてみることだけだった。
手始めに、数日かけていくつか実験をし、玉について次の事が分かった。
・昼間別の場所へ持ち出すことは可能
・どこへ捨てても翌朝には彼女の元へ戻る
・彼女が別の場所に泊まると朝までにそこへ移動する
・彼女にしか声は聞こえない
・多少の衝撃では壊れない
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
¥550 税込
SOLD OUT