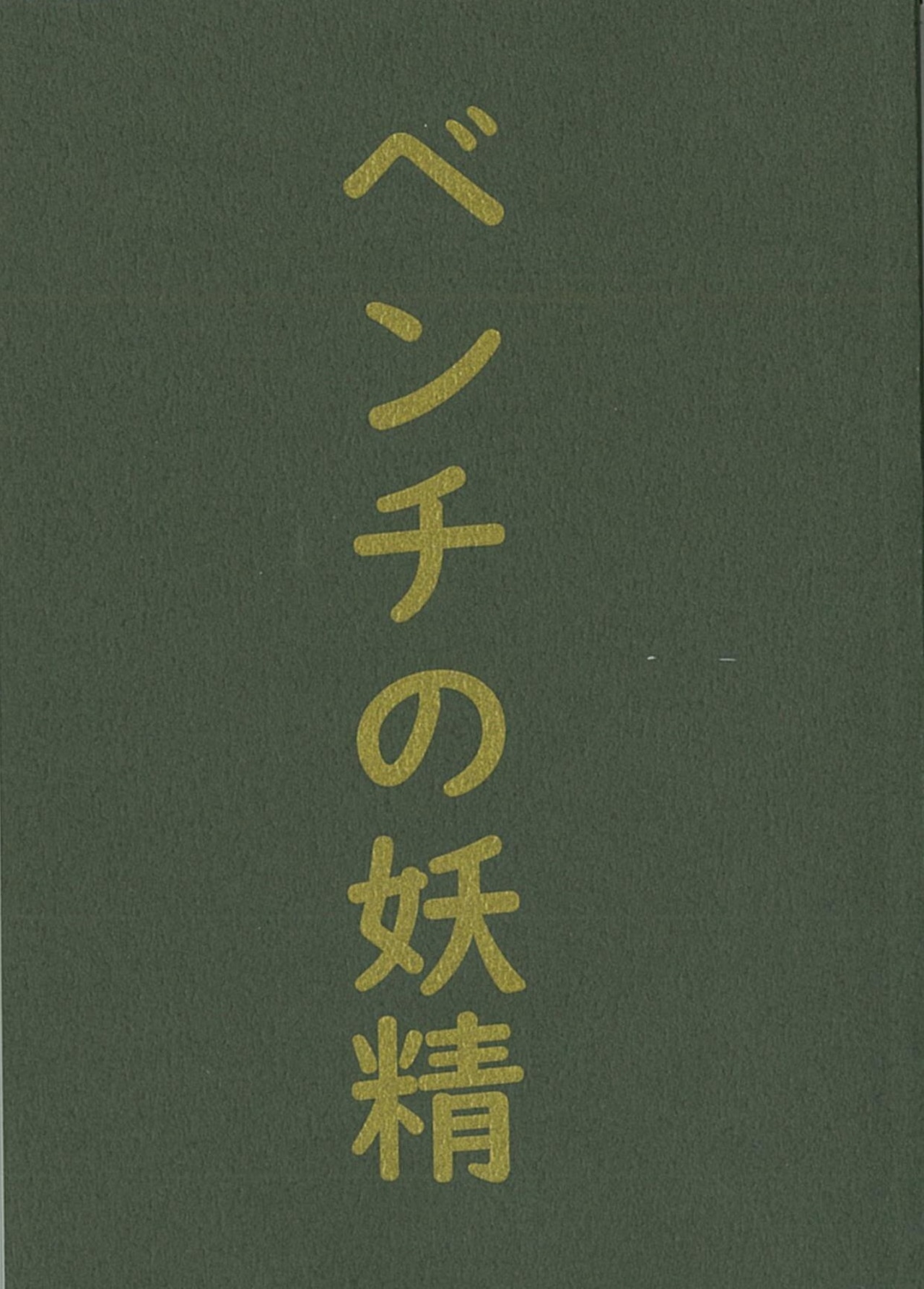
ベンチの妖精
¥650 税込
SOLD OUT
送料が別途¥370かかります。
サークル名:チューリップ庵
作家・アーティスト名:瑞穂 檀
高校生のサチは、深夜の公園で小さな女の子と出会う。その子は自分を「ベンチの妖精」と言っていて…
上手くいかない昼間の学校生活と、夜の公園での少女とのふれあい。少し切ないファインタジー
------------------冒頭--------------------------
小さな公園にベンチがある。カラフルで新しいベンチは、日当たりの良い砂場の脇やブランコの前。一番古くて色の褪せたベンチは、公園の端っこの寒々とした日陰に所在無げに佇んでいる。
サチが小学校に上がる前は、公園の全部に陽が当たっていて、古いベンチもぽかぽかの陽気の中にあった。けれど今では、背後にマンションが建ってしまい、文字通り日陰の存在。冬の休日、新しいベンチは日差しの中で人々の憩いの場になっているのに、日陰のベンチは誰も座りたがらない。
その日。サチは、真夜中にふらりと外に出た。
一月の半ばである。真冬の深夜は、寒い。スウェットの上にジャージを着て、更にダウンジャケットを重ね着して。両手をポケットにつっこんで、家族に黙って玄関を出て。近くのコンビニに行くだけじゃ気分転換には足りないと思い、少し遠回りした。
吐く息が白いなぁと、必要以上に大きく息を吐きながら歩く。そして、その小さな公園に辿りついた。
集合住宅と隣り合わせで、東門は図書館の裏門と向かい合わせ。西門は二車線ある道路に面している。土日の午後に通りかかると、親子連れがちまちまと遊んでいるのだが、真夜中はさすがに人影が無い。
子供の頃にはブランコや滑り台で遊んだけれど、高校生になってからは、何かの拍子に通りかかるだけ。門柱の間を通り抜けたのは、久々だった。
ベンチが目に入った。古くて色あせたベンチ。
サチは瞬きをする。
ベンチに人影があったのだ。しかも、小さな女の子。
公園の時計に目をやる。二時半。夜の二時半は子供が遊んでいい時間じゃない。
女の子はベンチに座ってサチを見ていた。
短めのデニムのスカートに、フリースのジャケットを着ている。黒いタイツとボアのついたショートブーツを履いているけれど、それでも寒そうな格好だ。
サチは、ベンチに歩み寄る。
女の子はベンチに座ったまま、にこにこしながらサチを見上げた。くっきりした瞳が可愛らしい。黒い髪は豊かで、華奢な背中を腰まで覆っていた。
「何してんの?」
尋ねるサチの声は、少し震えた。寒いのだ。歯茎が凍えそう。
答える女の子の声は、涼やかで落ち着いていた。
「座って、見ているの」
「何を?」
「色々なもの。今は、お姉さんを見ているの」
なんだか屁理屈ぽいが、女の子の表情も声も、とても素直だった。
小学校の三年生くらいかなと、サチは女の子の年齢に当たりを付ける。
「帰らないの? 親、心配してない?」
「お姉さんこそ帰らないの? おうちの人が心配してない?」
「寝てるから気が付いてないよ。ていうか、私とあなたは違うの。歳がぜんっぜん違うから。子供は家で寝てなきゃだめで、高校生はふらふら外を歩きたい年頃なの」
女の子は「子供じゃないよ」と笑った。
「私、ベンチの妖精なの」
「はぁ?」
「見て。口のとこ、よ~く見てね」
女の子は大きく口を開けて、これ見よがしに息をはぁっと吐いてみせる。温かな息は冷たい空気に冷やされて、白い雲のように口から出て……こなかった。サチの口からはひっきりなしに白い息が吐きだされているのに、女の子の口元にはなんにもない。
「あれ?」
女の子はサチの気が済むまで、「はぁっ、はぁ~!」と息を吐いて見せて。サチが諦めてベンチの端っこに腰をかけると、満足そうに「ほらね」と言った。
「幽霊?」
「違う。妖精なの」
「ベンチの妖精なんているの?」
「いるじゃない、ここに」
いまいち会話にならない。とはいえ、このまま置いていっていいものだろうか。
「家はどこ?」
女の子は小首を傾げて、答える。
「そこのマンション」
古びたベンチの後ろには、小さな花壇とフェンスがある。その向こう側、昼間なら丁度ベンチに当たる陽を遮る位置に、中層マンションが建っていた。
サチが子供の頃に建ったものだ。
「こっそり出てきたの? お母さん、寝てるの?」
「そう、こっそり。お姉さんもそうでしょ? 同じね」
大人っぽい落ち着いた口調と、整った姿と、白くない息。サチはこの子が、本当に妖精のような気がしてきた。
「お姉さん、名前はなんていうの?」
「ん? サチ。あんたは?」
「妖精」
全くふざけている。信じそうになる自分に腹が立って、サチは「冗談言わないで」ときつめに窘めた。
「早く家に帰んなさい。お布団に居ないのがわかったら、親がびっくりするから」
勢いよく立ちあがり公園の出口に向かうサチの背中に、女の子は言う。
「ねえ、また遊びに来て。夜は誰もいなくて寂しいの」
「昼間に来ればいいじゃない」
「昼間は出てこられないの。だって妖精だから」
本当にばかばかしい。サチは早足で家に帰り、寝た。
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
¥650 税込
SOLD OUT













